「新しい海洋文化」の創造にチャレンジし、お役様に喜んでいただける商品を提供していきながら、広く社会に貢献出来ることを念願しています。
赤穂化成株式会社
「赤穂化成株式会社」と室戸のつながり
-
青のりの最高峰、すじ青のり
 室戸の深海の恵みを食卓へ!青のりの最高峰『すじ青のり』があなたの料理に魔法をかける。 「すじ青のり」とは、青のりの中でも香り・色・口どけが最も優れた極上の品種です。 香り成分が他種よりも豊富で和洋を問わず幅広い料理と調和し、食卓に豊かな風味と彩りを添えます。その存在感は、地元の食文化に深く根ざし、ひとふりで料理の印象を一変させて、ワンランクもツーランクも上の料理に変えてくれます。 かつて、四万十川流域は国内シェア90%を誇る一大産地でした。しかし、水温の上昇など環境の変化により、天然のすじ青のりは激減してしまいました。 「青のりの最高峰」とも称されるこの希少な海藻を復活させるべく、高知大学海洋植物学研究所は海洋深層水を活用した養殖技術を開発。 平成16年(2004年)、室戸岬町高岡漁港にて陸上養殖が本格的に始まりました。 流入する大都市河川もなく綺麗な室戸の海。その海底の断崖を湧昇流が運んできた1000m以深の海流を深度344mからポンプでくみ上げる海洋深層水は、清浄でミネラルが豊富。藻の成長に理想的な環境で、安定的かつ持続可能な養殖が可能となっています。 ある生産者はこう語ります。 「ある程度育つと、養殖池に養分を追加する必要はありません。自然の“海洋深層水”そのものが海苔の養分となるのです。まさに、室戸の海がもたらす恵みです。藻の成長に合わせ、水槽を入れ替えて適切な密度に管理していきます。」 成熟した青のりから胞子を採取し、ていねいに培養。深層水の清浄性により雑味が抑えられた養殖品は、青のり本来の香りと味わいを最大限に引き出し、「室戸の味」として特産品や土産品として定着しています。 室戸産のすじ青のりは、一年を通して安定供給が可能。季節に左右されず、香り・色・口どけのすべてにおいて高品質を保っています。 さらに、カルシウム・鉄分・マグネシウム・ビタミンA・B2・C・Eなどを豊富に含む、栄養価にも優れた海藻です。 市内では原藻・粉末タイプなどが販売され、観光客のお土産としても人気を集めています。 また、ふるさと納税の返礼品にも採用され、室戸ブランドの中核を担う存在として全国から注目を集めています。 室戸の豊かな自然と人々の情熱が育てた「すじ青のり」。 そのひと片には、海洋深層水の生命力と室戸の文化が織り込まれています。 料理に添えるたび、海と人のつながりを感じながら、私たちの暮らしにそっと彩りを加えてくれることでしょう。
室戸の深海の恵みを食卓へ!青のりの最高峰『すじ青のり』があなたの料理に魔法をかける。 「すじ青のり」とは、青のりの中でも香り・色・口どけが最も優れた極上の品種です。 香り成分が他種よりも豊富で和洋を問わず幅広い料理と調和し、食卓に豊かな風味と彩りを添えます。その存在感は、地元の食文化に深く根ざし、ひとふりで料理の印象を一変させて、ワンランクもツーランクも上の料理に変えてくれます。 かつて、四万十川流域は国内シェア90%を誇る一大産地でした。しかし、水温の上昇など環境の変化により、天然のすじ青のりは激減してしまいました。 「青のりの最高峰」とも称されるこの希少な海藻を復活させるべく、高知大学海洋植物学研究所は海洋深層水を活用した養殖技術を開発。 平成16年(2004年)、室戸岬町高岡漁港にて陸上養殖が本格的に始まりました。 流入する大都市河川もなく綺麗な室戸の海。その海底の断崖を湧昇流が運んできた1000m以深の海流を深度344mからポンプでくみ上げる海洋深層水は、清浄でミネラルが豊富。藻の成長に理想的な環境で、安定的かつ持続可能な養殖が可能となっています。 ある生産者はこう語ります。 「ある程度育つと、養殖池に養分を追加する必要はありません。自然の“海洋深層水”そのものが海苔の養分となるのです。まさに、室戸の海がもたらす恵みです。藻の成長に合わせ、水槽を入れ替えて適切な密度に管理していきます。」 成熟した青のりから胞子を採取し、ていねいに培養。深層水の清浄性により雑味が抑えられた養殖品は、青のり本来の香りと味わいを最大限に引き出し、「室戸の味」として特産品や土産品として定着しています。 室戸産のすじ青のりは、一年を通して安定供給が可能。季節に左右されず、香り・色・口どけのすべてにおいて高品質を保っています。 さらに、カルシウム・鉄分・マグネシウム・ビタミンA・B2・C・Eなどを豊富に含む、栄養価にも優れた海藻です。 市内では原藻・粉末タイプなどが販売され、観光客のお土産としても人気を集めています。 また、ふるさと納税の返礼品にも採用され、室戸ブランドの中核を担う存在として全国から注目を集めています。 室戸の豊かな自然と人々の情熱が育てた「すじ青のり」。 そのひと片には、海洋深層水の生命力と室戸の文化が織り込まれています。 料理に添えるたび、海と人のつながりを感じながら、私たちの暮らしにそっと彩りを加えてくれることでしょう。 -
高知県海洋深層水研究所
海洋深層水の資源的有効性の実証とその実用化をめざして、産・学・官の連携のもと、多分野において基礎から応用まで幅広い研究を進めています。(高知県) -
旅する牡蠣の秘密
 室戸海洋深層水で磨かれた味ー最高峰の「旅する牡蠣」 室戸の〈プライムオイスター〉は、まるで旅をするように産地をめぐる—そんなドラマを秘めたブランド牡蠣です。 海洋深層水という神秘的な海の力によって磨き上げられたこの牡蠣は、食卓に届くまでの物語も含めて、極めてユニークな存在です。 室戸沖の海は、生活排水が流れ込む大河川が存在せず、凛とした清らかさを保っています。さらに海底が急峻な断崖となっているため、太陽光が届かない深海から湧き上がる水—それこそが海洋深層水。水深1,000メートルから湧昇流として運ばれてくるこの水には、植物プランクトンに消費されずに残されたミネラルが豊富に蓄えられており、室戸の海産物に理想的な環境をもたらしています。 プライムオイスターを生産している赤穂化成株式会社の川島さんはこう語ってくれました。 「牡蠣の清浄性と味の両立によって付加価値を高めるために、この室戸の海洋深層水の地まで牡蠣を旅させているんです」 「生食用にするために必要な時間は48時間程度ですけど、長期間ミネラル豊富な海洋深層水に浸すことで、牡蠣をより美味しくしています」 「旅」という言葉が示す通り、室戸で行われているのは“畜養”。兵庫県・坂越の海域で育った牡蠣を室戸へ運び、海洋深層水に長期間浸すことで、旨みを引き出し“ととのえる工程”が施されます。 いわば、牡蠣の“デトックス”ともいえるこの工程が、味と安全性の両方を飛躍的に高めてくれるのです。 厚生労働省が定める生食用牡蠣の水質基準は極めて厳格ですが、室戸の海洋深層水はその基準をしっかりとクリア。しかも、ミネラルが豊富なその水が、牡蠣に新たな旨みを与え、プレミアムな味わいへと昇華させてくれます。薬剤に頼ることなく、安全と美味しさを両立するこのプロセスを経て、坂越産の牡蠣は「室戸のプレミアムオイスター」として新たな命を吹き込まれるのです。 今、室戸市では海洋深層水の利活用が多分野に広がりつつあります。製塩、養殖、飲料開発など、海の資源を活かした取り組みのなかで、「プライムオイスター」はまさに“新しい海洋文化”の象徴的存在。 訪れた際には、室津港すぐの「港の上」釜飯の名店「初音」で味わえますし、ふるさと納税を通じて自宅に迎えることも可能です。 潮の香りを感じながら、「旅する牡蠣」に想いを馳せてみてはいかがでしょうか。
室戸海洋深層水で磨かれた味ー最高峰の「旅する牡蠣」 室戸の〈プライムオイスター〉は、まるで旅をするように産地をめぐる—そんなドラマを秘めたブランド牡蠣です。 海洋深層水という神秘的な海の力によって磨き上げられたこの牡蠣は、食卓に届くまでの物語も含めて、極めてユニークな存在です。 室戸沖の海は、生活排水が流れ込む大河川が存在せず、凛とした清らかさを保っています。さらに海底が急峻な断崖となっているため、太陽光が届かない深海から湧き上がる水—それこそが海洋深層水。水深1,000メートルから湧昇流として運ばれてくるこの水には、植物プランクトンに消費されずに残されたミネラルが豊富に蓄えられており、室戸の海産物に理想的な環境をもたらしています。 プライムオイスターを生産している赤穂化成株式会社の川島さんはこう語ってくれました。 「牡蠣の清浄性と味の両立によって付加価値を高めるために、この室戸の海洋深層水の地まで牡蠣を旅させているんです」 「生食用にするために必要な時間は48時間程度ですけど、長期間ミネラル豊富な海洋深層水に浸すことで、牡蠣をより美味しくしています」 「旅」という言葉が示す通り、室戸で行われているのは“畜養”。兵庫県・坂越の海域で育った牡蠣を室戸へ運び、海洋深層水に長期間浸すことで、旨みを引き出し“ととのえる工程”が施されます。 いわば、牡蠣の“デトックス”ともいえるこの工程が、味と安全性の両方を飛躍的に高めてくれるのです。 厚生労働省が定める生食用牡蠣の水質基準は極めて厳格ですが、室戸の海洋深層水はその基準をしっかりとクリア。しかも、ミネラルが豊富なその水が、牡蠣に新たな旨みを与え、プレミアムな味わいへと昇華させてくれます。薬剤に頼ることなく、安全と美味しさを両立するこのプロセスを経て、坂越産の牡蠣は「室戸のプレミアムオイスター」として新たな命を吹き込まれるのです。 今、室戸市では海洋深層水の利活用が多分野に広がりつつあります。製塩、養殖、飲料開発など、海の資源を活かした取り組みのなかで、「プライムオイスター」はまさに“新しい海洋文化”の象徴的存在。 訪れた際には、室津港すぐの「港の上」釜飯の名店「初音」で味わえますし、ふるさと納税を通じて自宅に迎えることも可能です。 潮の香りを感じながら、「旅する牡蠣」に想いを馳せてみてはいかがでしょうか。 -
サツキマスの陸上養殖
 室戸の海洋深層水が育てた“プラチナサツキマス” ─幻の味を未来へつなぐ地域再生プロジェクト 室戸の「プラチナサツキマス」は、幻の魚・サツキマスを海洋深層水で育てる、先進的かつ挑戦的な陸上養殖プロジェクトです。 サツキマスは、美しい川で生まれ、豊かな海で育ち、再び川へと帰る“回遊するアマゴ”です。その希少性と繊細な味わいから「幻の魚」とも称されます。 かつては高知県の川や海でも見ることができました。しかし、河川環境の変化により天然個体は激減し、今では“幻の魚”とまで呼ばれる存在に。 室戸では、この貴重な魚を未来につなげようと、海洋深層水を活用した陸上養殖に挑戦しています。 室戸は、生活排水の流れる大河川がなく、海はひときわ清らか。 さらに、海底が断崖になっているため、太陽光が届かない深海から湧昇流として運ばれてくる水—それが水深1000mから昇ってくる海洋深層水。 この水には、植物プランクトンによって消費されずに残されたミネラルが蓄積されており、室戸の養殖に理想的な条件をもたらしています。 この深層水は水深344mからポンプで汲み上げられ、この清浄な海洋深層水のおかげで、薬剤を使わずに陸上養殖を行うことが可能になりました。そのため食の安全性を確保した上で、高品質な魚を育てることができるのです。 養殖を担うのは赤穂化成株式会社。高知県海洋深層水研究所や室戸漁業指導所と連携し、2020年にはついに約500尾の出荷に成功。 「室戸プラチナサツキマス」としてブランド化され、地域の希望として注目を集めました。 生産者は語ります— 「成長に合わせて水槽内の密度を調整し、ストレスの少ない環境を整えています。天然ものは旬が短いですが、海洋深層水の恩恵により、極上の“旬”を長く味わえる魚に育てています」 銀色に輝く魚体は、“プラチナ”の名にふさわしく、目を見張る美しさ。マリネ、箱鮨、焼き物、煮物など、和洋を問わずあらゆる料理にマッチし、上品な甘みとしっとりとした食感が絶品です。 海洋深層水を活用したサツキマス養殖は、海洋深層水は年間を通して安定した低温なため、水温管理に必要なコストと環境負荷を抑えられるという環境配慮型のモデルとしてだけでなく、室戸高校との連携による教育プログラムや、地域雇用やブランド振興にも貢献しています。 地域おこし協力隊との協働プロジェクトにて「にっぽんの宝物 世界大会」への出場。室戸高校の生徒による商品開発やPR活動など積極的な活動が注目されます。 室戸産のこの極上サーモンは、今後、地元のホテルや飲食店で提供されるなど、地元消費が進むことで、地域活性化の起爆剤となる期待も高まっています。 「幻の魚」を次世代へとつなぐこの取り組みは、まさに室戸の新たな海洋文化の象徴となりつつあるのです。
室戸の海洋深層水が育てた“プラチナサツキマス” ─幻の味を未来へつなぐ地域再生プロジェクト 室戸の「プラチナサツキマス」は、幻の魚・サツキマスを海洋深層水で育てる、先進的かつ挑戦的な陸上養殖プロジェクトです。 サツキマスは、美しい川で生まれ、豊かな海で育ち、再び川へと帰る“回遊するアマゴ”です。その希少性と繊細な味わいから「幻の魚」とも称されます。 かつては高知県の川や海でも見ることができました。しかし、河川環境の変化により天然個体は激減し、今では“幻の魚”とまで呼ばれる存在に。 室戸では、この貴重な魚を未来につなげようと、海洋深層水を活用した陸上養殖に挑戦しています。 室戸は、生活排水の流れる大河川がなく、海はひときわ清らか。 さらに、海底が断崖になっているため、太陽光が届かない深海から湧昇流として運ばれてくる水—それが水深1000mから昇ってくる海洋深層水。 この水には、植物プランクトンによって消費されずに残されたミネラルが蓄積されており、室戸の養殖に理想的な条件をもたらしています。 この深層水は水深344mからポンプで汲み上げられ、この清浄な海洋深層水のおかげで、薬剤を使わずに陸上養殖を行うことが可能になりました。そのため食の安全性を確保した上で、高品質な魚を育てることができるのです。 養殖を担うのは赤穂化成株式会社。高知県海洋深層水研究所や室戸漁業指導所と連携し、2020年にはついに約500尾の出荷に成功。 「室戸プラチナサツキマス」としてブランド化され、地域の希望として注目を集めました。 生産者は語ります— 「成長に合わせて水槽内の密度を調整し、ストレスの少ない環境を整えています。天然ものは旬が短いですが、海洋深層水の恩恵により、極上の“旬”を長く味わえる魚に育てています」 銀色に輝く魚体は、“プラチナ”の名にふさわしく、目を見張る美しさ。マリネ、箱鮨、焼き物、煮物など、和洋を問わずあらゆる料理にマッチし、上品な甘みとしっとりとした食感が絶品です。 海洋深層水を活用したサツキマス養殖は、海洋深層水は年間を通して安定した低温なため、水温管理に必要なコストと環境負荷を抑えられるという環境配慮型のモデルとしてだけでなく、室戸高校との連携による教育プログラムや、地域雇用やブランド振興にも貢献しています。 地域おこし協力隊との協働プロジェクトにて「にっぽんの宝物 世界大会」への出場。室戸高校の生徒による商品開発やPR活動など積極的な活動が注目されます。 室戸産のこの極上サーモンは、今後、地元のホテルや飲食店で提供されるなど、地元消費が進むことで、地域活性化の起爆剤となる期待も高まっています。 「幻の魚」を次世代へとつなぐこの取り組みは、まさに室戸の新たな海洋文化の象徴となりつつあるのです。 -
海洋深層水からの製塩
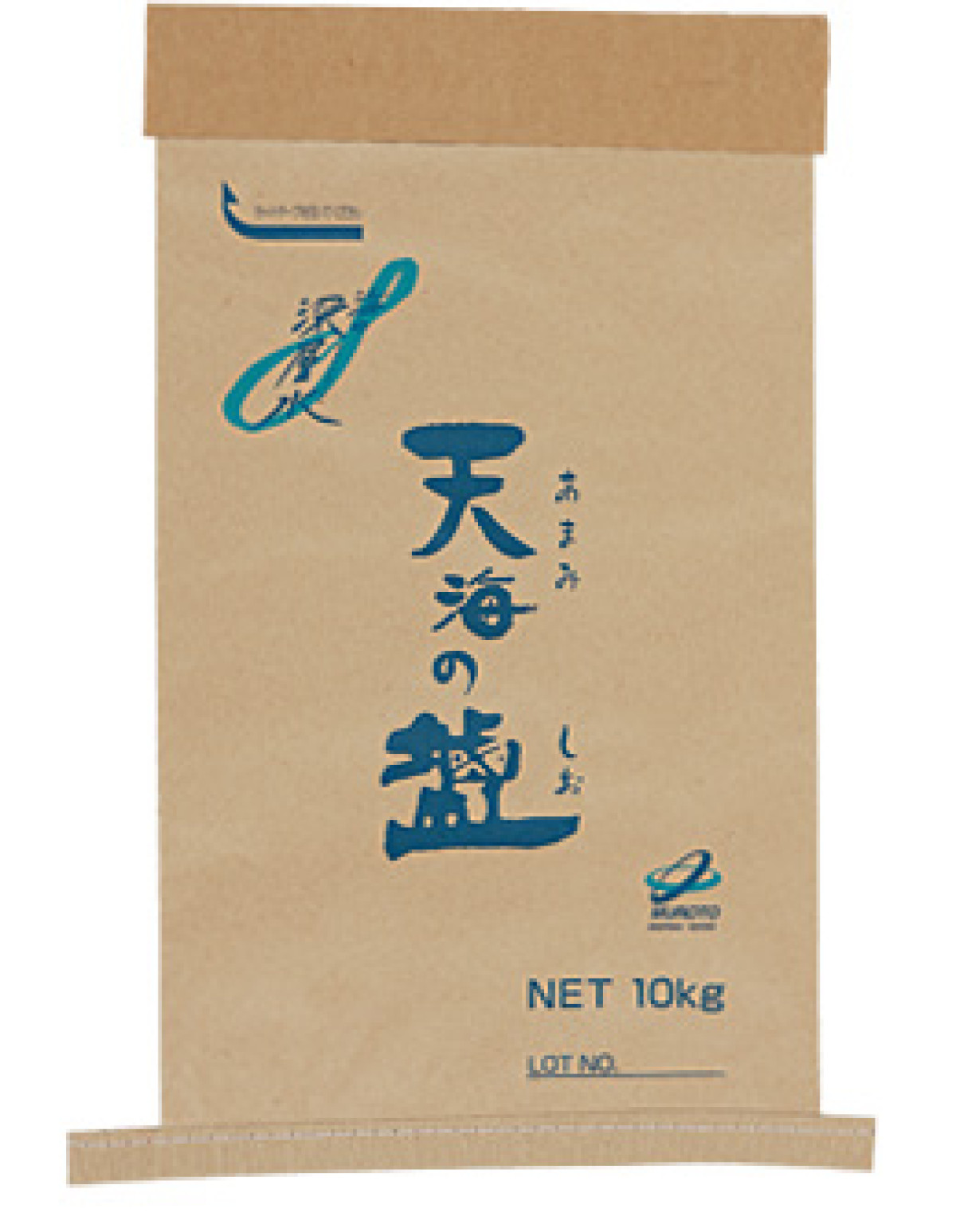 料理の味が変わる!深海の恵みが生んだ「天然ミネラル塩」の威力 室戸のお土産で、まずオススメしたいのが海洋深層水からつくられたお塩です。その味わいは、一般的な食塩とはまるで別物。あまりに違うので、「ウチの子が塩がいつもと違うって気づいたのよ」とお塩を贈った人に驚かれることもあるほどです。 料理好きな方や、“味の違いが分かる人”にもこの塩は大好評。毎日の食卓に少し添えるだけで、素材の味がふわっと引き立ちます。 室戸沖の深海、太陽の光が届かない水深1000mから湧昇流が運んできた海洋深層水。 そこには、植物プランクトンが光合成をしないため、消費されずに残されたミネラルがたっぷり蓄積された海水が眠っています。この「海の記憶」とも言える深層水を水深344mからポンプで汲み上げ、濃縮して結晶化。生産者の方いわく、「海洋深層水にもともと含まれるミネラルをどう残すかが塩づくりの真髄」なのだそうです。 だから、この塩にはミネラルの旨味が際立ちます。 私自身、毎日の料理に使っていますが、少しふりすぎてしまっても「しょっぱさ」で失敗することがありません。それは、塩の中にコクとまろやかさ、そして余韻のある旨味が含まれているからでしょう。 「室戸の海洋深層水のお塩」は、料理の用途や食材の個性に合わせて選べる豊富なラインナップも魅力です。 たとえば、天ぷらや焼き物、トマトなどの素材をダイレクトに味わいたい料理には、にがりを残したしっとりタイプの塩がおすすめ。しっかりとした塩味に、ほんのりと甘味が重なるまろやかな味わいが特徴で、素材の持ち味をふんわりと引き立てます。 一方、梅干しやパン、干物づくりなど、塩をたっぷり使う料理には、粒子の細かいしっとりタイプの塩がぴったりです。塩の風味が穏やかに馴染むので、素材の良さを損なうことなく、繊細な仕上がりが得られます。 そして、料理の仕上げにひとつまみ添えるなら、太陽熱でゆっくりと結晶化させた天日塩が最高です。ミネラルをしっかりと残したこの塩は、ひと粒ひと粒に深みがあり、余韻のある味わいが料理全体を引き締めてくれます。 それぞれの塩が、“ただの調味料”を超え、料理を豊かにする存在として寄り添ってくれるのです。 室戸では、海洋深層水を活用した製塩事業が地域の未来を支える柱にもなっています。 地元企業の室戸海洋深層水株式会社は、高知工科大学との共同研究を通じて、にがみ成分をほぼ除去しながら、ミネラルを活かす独自技術を確立。 この塩づくりは、過疎化対策の一環としても位置づけられており、雇用の創出・地域資源の活用・地元ブランドの確立へとつながっています。 室戸海洋深層水のお塩は、太古の海が育んだ栄養と、室戸の人々の技術と情熱が凝縮された結晶。それは、毎日の料理をそっと支え、食卓に静かに寄り添ってくれる一粒の奇跡です。
料理の味が変わる!深海の恵みが生んだ「天然ミネラル塩」の威力 室戸のお土産で、まずオススメしたいのが海洋深層水からつくられたお塩です。その味わいは、一般的な食塩とはまるで別物。あまりに違うので、「ウチの子が塩がいつもと違うって気づいたのよ」とお塩を贈った人に驚かれることもあるほどです。 料理好きな方や、“味の違いが分かる人”にもこの塩は大好評。毎日の食卓に少し添えるだけで、素材の味がふわっと引き立ちます。 室戸沖の深海、太陽の光が届かない水深1000mから湧昇流が運んできた海洋深層水。 そこには、植物プランクトンが光合成をしないため、消費されずに残されたミネラルがたっぷり蓄積された海水が眠っています。この「海の記憶」とも言える深層水を水深344mからポンプで汲み上げ、濃縮して結晶化。生産者の方いわく、「海洋深層水にもともと含まれるミネラルをどう残すかが塩づくりの真髄」なのだそうです。 だから、この塩にはミネラルの旨味が際立ちます。 私自身、毎日の料理に使っていますが、少しふりすぎてしまっても「しょっぱさ」で失敗することがありません。それは、塩の中にコクとまろやかさ、そして余韻のある旨味が含まれているからでしょう。 「室戸の海洋深層水のお塩」は、料理の用途や食材の個性に合わせて選べる豊富なラインナップも魅力です。 たとえば、天ぷらや焼き物、トマトなどの素材をダイレクトに味わいたい料理には、にがりを残したしっとりタイプの塩がおすすめ。しっかりとした塩味に、ほんのりと甘味が重なるまろやかな味わいが特徴で、素材の持ち味をふんわりと引き立てます。 一方、梅干しやパン、干物づくりなど、塩をたっぷり使う料理には、粒子の細かいしっとりタイプの塩がぴったりです。塩の風味が穏やかに馴染むので、素材の良さを損なうことなく、繊細な仕上がりが得られます。 そして、料理の仕上げにひとつまみ添えるなら、太陽熱でゆっくりと結晶化させた天日塩が最高です。ミネラルをしっかりと残したこの塩は、ひと粒ひと粒に深みがあり、余韻のある味わいが料理全体を引き締めてくれます。 それぞれの塩が、“ただの調味料”を超え、料理を豊かにする存在として寄り添ってくれるのです。 室戸では、海洋深層水を活用した製塩事業が地域の未来を支える柱にもなっています。 地元企業の室戸海洋深層水株式会社は、高知工科大学との共同研究を通じて、にがみ成分をほぼ除去しながら、ミネラルを活かす独自技術を確立。 この塩づくりは、過疎化対策の一環としても位置づけられており、雇用の創出・地域資源の活用・地元ブランドの確立へとつながっています。 室戸海洋深層水のお塩は、太古の海が育んだ栄養と、室戸の人々の技術と情熱が凝縮された結晶。それは、毎日の料理をそっと支え、食卓に静かに寄り添ってくれる一粒の奇跡です。 -
室戸海洋深層水アクア・ファーム
 海洋深層水は、地球の両極付近の海で生まれ、遙かな時間をかけてゆっくりと循環しています。 室戸市は1985年に科学技術庁(現:文部科学省)アクアマリン計画のモデル海域指定を受け、1989年に日本初の海洋深層水研究所が、室戸岬町三津に設立されました。(室戸市HPより) そして2000年4月には海洋深層水のさらなる研究と事業化を目指して室戸岬町高岡に「アクア・ファーム」が誕生しました。
海洋深層水は、地球の両極付近の海で生まれ、遙かな時間をかけてゆっくりと循環しています。 室戸市は1985年に科学技術庁(現:文部科学省)アクアマリン計画のモデル海域指定を受け、1989年に日本初の海洋深層水研究所が、室戸岬町三津に設立されました。(室戸市HPより) そして2000年4月には海洋深層水のさらなる研究と事業化を目指して室戸岬町高岡に「アクア・ファーム」が誕生しました。
